頸城野点景
農作業の女性は格好良い。
本日日曜日の頸城野は穏やかに晴れ、随所に農作業が見
られた。
本日あらためて感じたのは作業をする女性の生き生きとし
た格好良さだった。
それに女性がいるだけで、現場が明るく見えるのである。
いっそ都会の女性達も作業服を着て農地に出れば、
一段と健康的で素晴らしい魅力を放つと思う。
そんな時代が来ればいいのに、、、もったいないなあ。
海への跨線橋が架け替えられた海崎海岸。
まだ風が収まりきらない土曜日午後、柿崎海岸を歩いた。
海岸沿いの道にハマエンドウの紫の花が盛りだった。
JR線を渡る橋が気持ち良く架け替えられている。
海あり里あり田んぼありの当地は近隣で不自由なく楽める。
頸城平野は田植えの時期に。
良く晴れたが終日風が強かったこどもの日の祝日。
昼過ぎには当地の東、米山と尾神岳に長々としたレンズ
雲が見られた。
当地の水田で代掻き(しろかき)が始まっている。
代掻きは田に水を張って耕す作業だが、均等に土を起こし、
水平を保ち、雨にも配慮するなどこまやかな仕事だという。
担い手には大変なことと考えられるが、水田は当地の貴重
な景観。
折々にきれいに草が刈られ、広々として本当に美しい眺めだ。
間もなく頸城平野一面に水が入り初々しい苗が植えられる。
明日も強風の予報が出ている。
四度目の蜘蛛ケ池道(瑞天寺-十二神社) 独立自知 馬鹿野郎大居士という墓碑銘。
樹下美術館の近くに大潟スマートインターがあり、周
辺は雑木林に囲まれている。
その林の中に小径があり、十二神社から三つの鳥居を
経てほくほく線高架橋をくぐり、蜘蛛ケ池は瑞天寺へ
とジグザクに続いている。
昨年10月に偶然この道を見つけ、神仏をつなぐ静け
さと路傍の草花が気に入り何度か歩いた。
2015年10月22日
本日来館されたご夫婦は過去のブログで道に興味を持
たれ、急遽「行って見ましょうか」ということでご一緒した。
私が知らないことを教えてもらったり新たな発見もあり楽
しかった。
このたび勝手に蜘蛛ケ池道と呼んでみることにした。

↑本日一段と緑深くなった道。
草刈りなどは蜘蛛ケ池集落の方達がされていると聞いた。

↑ニホンタンポポ(ほかではおおかた西洋タンポポということですが、
この道のはみなニホンタンポポらしい)

↑瑞天寺裏山の墓所にある笠原家の墓。
大傷みしていて非常にもったいない。

↑墓所にある笠原大川の墓碑(勝海舟筆による「大川笠原
君墓碑銘」の八文字(昭和63年発行大潟町史を参考)。

↑驚かされた「独立 自知 馬鹿野郎大居士」と記された
墓碑。
瑞天寺の墓地は檀家衆の非常に立派な墓が多い。
その中の一つで、安政五年の年号があった。
自ら名乗ったものか、残された人の命名なのか。
どんな人だったのだろう、独立自知の言葉はとても
良い。
いずれにしてもこれ以上無い謙遜?の墓碑であろう。
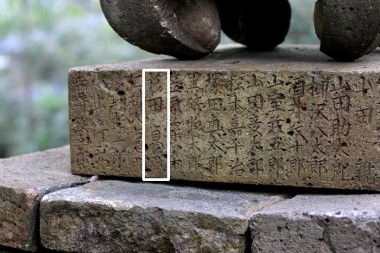
↑笠原家墓地の入り口にあった二基の灯籠のうちの一基。
寄進者の名の中に曾祖父貞蔵(嘉永3年11月28日生まれ、
嘉永3年→1850年)の名があった。
貞蔵の父玄作は笠原大川(だいせん)の弟子の一人であり、
大川に勧められて医師になっている。
(玄作の娘トヨは小山作之助の母です)
本日はご一緒した方のお陰でニホンタンポポ、馬鹿野郎
大居士の墓、曾祖父の彫り銘など興味深い発見をさせて
もらった。
500メートルほどの短い小径だがいつもなにかしら楽し
める。
途中ほくほく線高架橋の真下を抜け、頭上を電車が通った。
百合の群生も見つかり夏にはどんな花が見られるだろう。
いつか皆様とご一緒にここを歩いてみたいと思いました。
拙ブログを楽しみにしていると仰る入院中のAさん、ご覧い
ただけましたでしょうか。
治療に専念され、ご快癒されることを心よりお祈りしていま
す。
本日は一夫一妻のキジ 緑の蜘蛛ヶ池
昨日は二羽の雌と一羽の雄による睦まじいつがい?を記載
した。
そしてキジは一夫多妻と書かせて頂いた。
その筆の先も乾かぬうちに本日は一夫一妻のキジに出会った。
こちらの方が落ち着く感じだったが、この先まだ奥さんが増え
そうな予感もする。
場所は樹下美術館の近く、上越市大潟区は蜘蛛ヶ池のあぜ
道だった。
このところ鳥ばかりで、美術館館長の内容としていささか問題
であろう。

↑日射しの中、雄はいっそうあでやかで、一方雌に鬼気迫る真剣
さが見られた。
(だが雄の眼差しは滑稽で真剣みが無い。そのことが余計に雌を
惹きつけるのか、今で言えばチャラ男の骨頂かもしれない)。
キジの後、目と鼻の先にある蜘蛛ケ池を訪ねた。
ここで終わるはずだったが、、、。

↑向こうからコブハクチョウが岸辺に寄ってきた。
コブハクチョウはかって近くの鵜の池や朝日池で見ている。
いつも一羽だが同じ鳥なのだろうか。
連日の鳥(あるいは蝶)で背中に羽が生えそうだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日は風強く不安定なお天気で、午後の晴れ間の後に
雷が轟き激しい雨になり細かいアラレが混じった。
夜遅くも雷をともなう雨が降った。
上越市頸城区は茶臼山の春 オシドリもあらがう。
暖かく、野も花も鳥も春を謳歌した一日。
昼食後に近くの茶臼山の林道を車を走らせかつ歩いた。
樹下美術館から近く、小高い山を回る道は短いが、
下方に隠れるように沼があるため植生は豊かなようだ。

↑群生する小さなスミレ、こちらはツボスミレと言うらしい。
白っぽい花のサイズはタチツボスミレの半分くらい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
林道に行く前の用水池でオシドリを見た。
「ガーガー!」
メスの取り合いをしたらしく、一羽のオスが他のオスを威嚇した所だった。
追われたオスは堤に逃げ、追った方はメスに添った。
人もうらやむオシドリ夫婦とは言え修羅場があるらしい。
追われたオスはつがいを眺めていたが間も無く遠くへ飛び立った。
“つがはねどうつれる影をともとして
鴛鴦すみけりな山川の水”.
その昔、西行は孤独なオシドリを自らに重ねて歌っている。
長くなりました。
雑木林の草花 ズボンに止まったヒオドシチョウ 荒天のゴルフ。
昨秋、近くの雑木林に神社と寺を結ぶ小径を見つけて歩いた。
春に歩こうと考えていたので昨日空いた時間をみて散策した。
路傍の野の花が可憐だった。

↑花の写真を撮っていると蝶が来てズボンに止まった。
ヒオドシチョウということ。
羽がぼろぼろなのは越冬したためらしい。。
何処で冬を越すのか、またその間は冬眠するのだろうか。
痛んではいたが、元気よく飛んで行った。
昨年秋は沢山の赤とんぼがズボンに止まったが、今度は蝶とは。
いずれも白ズボンだった、トンボや蝶は白が好きなのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて本日は大荒れの一日。
ゴルフコンペが予定されていたが、集合時、多数決で中止になった。
しかし決行に賛成した四人でラウンドした。
ボールはキュウキュウと曲がったが、嵐の中パートナーシップが爽
やかで、お腹も空いた。

美術館の近くであたりを覆う畑の砂塵。
明日はガラス拭きと庭掃除が大変であろう。
吹き出すような新堀川の桜。
樹下美術館から10分ほど歩くと新堀川沿いの桜が見られる。
川は犀潟駅の東向こうを流れている。
何十年も前の町長の発案で川沿いに公園が作られ桜が植栽され、
風致公園の趣がある。
一体は雪が少ないため樹は伸び伸びと枝を伸ばし、吹き出すごと
く花に勢いがある。
以下は本日の写真です。
毎年シートを敷いた一団が花見をし、本日は施設の方達が車
椅子を並べ、若い自転車の女性がさっそうと走った。
また樹下美術館に来られると必ず帰りに寄られる県央のご夫婦が
おられ、先日は高田の人が滋賀県の方をお連れし、素晴らしかった、
と仰った。

↑なんという種類だろう、銀色の幹が何本も立ち上がって広がる。
若草とあいまって明るく清々しい。
満開を過ぎて間もなく花吹雪を迎えよう。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。
- 雪と車 そして選挙。
- 直江津、無印良品で。
- 2月の好天、期日前投票。
- 新たな倉石隆作品「節句」。
- 本日誕生日だった。
- 最近の妻の料理から、夕食。
- 道路を歩く雌キジ三羽。
- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。
- 道路に出てくる野鳥。
- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。
- 長くなりそうな本物の大寒。
- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。
- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。
- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。
- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。
- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。
- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。
- 寒波前の冬鳥たち。
- 届いたサントリーフラワーズのお花。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月



















































