頸城野点景
田も庭も待たれる雨。
数日晴れが続き、梅雨が開けている。
暦を見ればはや7月も残り少なくなった。
自分がボヤボヤしているうちに近隣の水田はすっかり成長している。
今頃の水田は例年緑ゆたかで生気にあふれてとても気持ちが良い。
見れば穂が出ている田も随所に見られ、それもびっしり付いている。
農家の方に聞いたが、今年はそもそも雪が少なく田を潤す水ガメの貯水が
足りず、現在大切な水に関してぎりぎりの状況だという。
干したり潤したり稲には微妙な時期にあり、ちゃんとした降水が必要なようだ。
樹下美術館の庭は基本的に砂地で、アジサイやクリスマスローズは暑さの
影響を受けやすく、当面気が抜けない。
そこへいくとムクゲやミソハギなどは暑さに強く頼もしい。
農場に若い人 無台風が続いている。
樹下美術館の南に隣接する水田、畑地は上越市大潟区の
ナショナルカントリー、通称ナショカンが営んでいる。
ベンチなどで見ていると季節毎の作物の移り変わりや農作
業を目にする事ができて興味深い。
キジが追っかけっこをしていた枝豆畑は青々と成長し同園で
は出荷が始っている。
さて去る23日、フィリッピン海域で台風の卵と呼ばれる熱帯
低気圧の発生が報じられたが、発達せず台風にはならなかっ
た模様。
今年になってまだその発表はなく、記録的な年の可能性が出
てきている。
熊本の復興には一日でも遅いまた弱い台風の年になるように
祈りたい。
頸城の海と里、梅雨の晴れ間の鬼舞と岩の原。
本日梅雨の晴れ間の日曜日、有志で糸魚川市鬼舞(きぶ)へ行った。
同地に江戸中期から明治期に北前船の回船業で栄えた県内有数の伊
藤家がある。
多数の船を有し大阪、瀬戸内、そして日本海沿岸および北海道の商業
港を巡る商いで成功を収めている。
同家のすぐ裏手の高所に五霊神社がある。
境内の鳥居や狛犬などの設えは広島県尾道の石であり、尾道の石工に
よって作られ、北前船ではるばる運ばれている。
蝦夷地へ米、藁、網、繊維、日用品などを運び、北海道で海産物、魚肥
小豆などを買い付けて商った。
同家の伊藤助右衛門[(1887~1967)は事業の近代化に取り組む一方
大正昭和期において富本憲吉(齋藤三郎の師でもある)と親交、民芸運
動作家たちの貴重なコレクターでもあった。

↑気持ち良く晴れた日本海を望む境内。
長大な日本海を帆走、険しい海峡や潮流を越えて商いをしたスケールの
大きな先人たちを誇りたい。

↑佐渡と能登を見ているような二体の狛犬の一体。
嘉永二年(1849年)と刻まれ、晴れ晴れとした姿だった。

↑備後(びんご)尾道 石工(いしく)惣八作とあった。
狛犬にしろ鳥居にしろ文字の彫りが異常に深い。
尾道の職人は当地の風を心配し、長く時経ても文字
が読めるよう苦心したのだろう。
お陰で今なお全く歴然として、微塵の風化も感じられ
ない。
尾道石の造作を見たあと伊藤家に寄ってご挨拶をした。
昔お目に掛かったお年寄りが元気に出てこられ、嬉し
かった。
その後上越市へ戻り岩の原葡萄園で食事、同園の石
蔵および雪室を見学した。

↑レストラン入り口に飾られたワイン「深雪花」と「善」。
二代陶齋(齋藤尚明)による色絵椿大皿を囲んで赤白、
そしてロゼが格調高く配されている。
賑わう店内で8名うち揃って美味しいランチを堪能し、
おしゃべりに夢中のあまりメニューの写真を失念。

↑森のかおりに包まれて熟成される明治31年建造第二号石蔵の赤ワイン樽。

↑ワイナリー開祖者川上善兵衛が開発した国産の名ワイン葡萄、
マスカットベーリーAが元気いっぱいに実を付けている。
これから順次房を選び実りの秋を迎える。
清々しい空の下、糸魚川の潮のかおり高田平野の森のかおりを吸
いながら心身のリフレッシュをした一日だった。
梅雨の庭 除草作業の美しい女性。
空梅雨かと思われた空だったが、このとこと梅雨らしくよく雨が降る。
肌寒い日は余計梅雨らしい。
このところ樹下美術館にしばしば新しい方達がお見えになる。
いちいちお尋ねしないが、どこでお知りになるのだろう、とても有り難い。
さて額アジサイの大方が終わってテッポウユリとカシワバアジサイ
が咲き誇ほこり、夏の女王を競っている。
いや、咲き競うなどと言っては花には失礼だ、お互い一生懸命咲いて
いるだけに違いない。

↑向こうが元からあったカシワバアジサイの親。
手前は5年ほど前に一本の芽を掘って移植した子で、随分大きくなった。

↑ほとほどの雨をよろこんでいるテッポウユリ。
淑女風の花だがいつも賑やかに見える。

↑今年の芝の成長は早い、もう何度目だろう、本日スタッフの芝刈り。
この後、ホームセンターから30キロほど肥料を買い、10キロ撒いたところで
雨となり中断した。

樹下美術館の付近の市道で草刈りが行われている。
明日には残された刈り草が除去されるはず。
ところでビシッとつなぎを着て、ヘルメットを被っていた作業員に驚いた。
横顔に口紅が見え、鼻筋通る美しい女性だった。
ぶんぶんうなる草刈り機を背よりも高く掲げ、木に絡んだ猛烈な葛も刈って
いた。
これは普通の人ではない。
写真を撮らせてと喉まで声が出かかったが、とても言えなかった。
瞽女ミュージアム高田 鵜の浜温泉の夕陽。
昨日土曜日午後は長く間懸案だった場所を訪ねた。
「瞽女ミュージアム高田(麻屋高野 上越市東本町1-2-33)」へ行った。
懐かしげな旅情を漂わせる一角で、すっかり楽しませてもらった。

「瞽女ミュージアム高田」はかって染物屋さんのだった町屋が
巧みに利用されている。
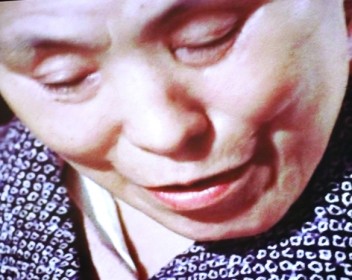
杉本キクイさん(館内の紹介映像から)。
この人がいなかったら文化としての「高田瞽女」の名実は
残らなかったかもしれない。
最後の瞽女(ごぜ)の覚悟を胸に昇華した美しい人だと思った。
とても強靱で聡明な印象を受ける。
瞽女さんには厳しいハンディキャップと芸が深く一体化されている

↑齋藤真一氏の装丁による本の数々。
(齋藤画伯の油絵を観たかったのだが)
以下は昨夕出会った鵜の浜温泉の夕景です。
大潟かっぱ祭 編み笠の米大舟。
当地に長く伝わる踊りに「米大舟(べいだいしゅう)」が
ある。
子供の頃の祭の夜、神社で輪踊りが行われていた。
この踊りも歌も好きで小学生のころよく見に行った。
哀愁の曲調を剽軽にを踊るオジさんがいて、お腹をか
かえて笑いながらその人に付いて回ったことがあった。
翌日、その人の踊りのこともあるが、真似をしながら
ついて歩いた私も可笑しかった、と人に言われた。
ところで昨日から明日まで上越市大潟区で「大潟
かっぱ祭」が開かれていて本日午後、米大舟が踊
られた。
以前から昔ながらの編み笠をかぶる踊りを是非見
たいと思っていたところ、今年実現した。

ああ懐かしい、今年は編み笠を被って踊った。
笠は踊りに専念出来るし、姿も動きもきれいに見える。

八社五社(やしゃごしゃ)を踊る人達も集合。
昔から地域によって八社五社が踊られている。
米大舟や八社五社でいえば、何百年前と同じようにするのは本
当にすばらしい。
それだけの価値を有していることと、伝える人と観る人も価値を
分かっていることで余計に素晴らしく思われる。
草が刈られている場所の清々しさ。
最高気温が20度に届かず、夕刻は15℃だったと当地のニュース
が伝えていた。
今年の花は早く咲きあっという間に終わってしまいますね、とある
方が仰った。
まさにその通りだと思う。
樹下美術館の庭は大好きなキョウガノコが華やかに、ヤマボウシ
は白さを増している。
うかうかしていたらアジサイがあちらこちらでパッパッと咲き始め
た。
周囲の空き地に目を移せばこんな庭が出来れば、と思うほど色と
りどりの草花が清々しい初夏の彩りを見せている。
以下三葉は美術館近傍の空き地です。

↑美術館から少し離れた場所でムシトリナデシコとマンテマの赤い
花が混ざり、チガヤの白い穂が忙しく風に揺れていた。
ところで空き地は放置すれば茂りに茂り、あっという間にジャングル
化する。
上記の場所はいずれも適時草刈りをしているため、風も陽も通り清々
と花が咲き、ピクニックをするか絵でも描いてみたくなる。
いずれも印象派絵画の草地のような色彩を帯びて美しかった。
昔から地域を知っている人はほどよい草刈りを欠かさない。
その方達のお陰で気持ち良い眺めに出会うことが出来る。
かって農村では牛馬の餌としてせっせと草刈りにいそしんだというが、
景観も大切にしたのではないだろうか。
頸城野の早苗と電車とツバメ 10年目の樹下美術館。
田植えを終えた水田の中をほくほく線の電車が行く。
かって高速特急「はくたか」が轟音と共に通り過ぎたほく
ほく線。
普通列車だけになったが、くびき駅を出てから目の前に現
れ雑木林に消えるまで、さえぎる物も無く眺めは楽しい。
日本一早いローカル特急を支えた高架橋は立派で、今そ
こを走る普通列車は田園の「小さな王子さま」といった感じ
だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日来館された何組かの方が、
「上越にこんな良い所があるなんて知らなかった」と仰った
そうです。
樹下美術館は今年10年目になりましたが、実はこの様な
ご感想がよく聞かれ、今なお大いなる励みになっています。
“皆様に感謝を致し、これからもどうか宜しくお願い申し上
げます”
清々しかった新潟県立大潟水と森公園。
5月になり強い寒暖や風に見舞われていがこの所穏やかに推移
するようになった。
午後休診の本日、4時半頃から新潟県立大潟水と森公園を歩いた。
今年1月に来た時、こんな所に道があるのか、と思った所を初め
て歩いた。
広大な園内の自然観察園ゾーンと潟の里ゾーンの一部を歩いた。
桑の実がつき、ヤマボウシが咲き、モミジは鮮やかだった。
華々しい花は無いが公園は緑したたる初夏を迎えていた。
沢山写真を撮ったが、繁茂の季節を前に行き届いた管理に感心さ
せられた
夕刻の園内を歩く人たちは健康そうだった。
若き日、お年寄りたちは早乙女として隣町の田植えに行った。
先日昭和10年生まれの方から、娘時代の何年か毎年、
隣町の農家に行き田植えをした話をお聞きした。
数日後昭和4年生まれの方が、同じ話をされたので、少々
驚いた。
お二人とも頸城区の農家から大潟区へ嫁がれている。
お話はいずれも実家に於ける娘時代の体験だった。
田植えをする娘さんたちは「しょうとめ?そーとめ?(早
乙女)」と呼ばれたらしい。
当時の年令と住所は異なっているが早乙女として田植え
に行った先は偶々いずれも現在の柿崎区の上直海(かみ
のうみ)だった。
お聞きした内容はおよそ以下のようなものだった。
15才~20才ころ田植えの時期が近づくと親は新しいカス
リの生地を買ってきて、娘達は自分で野良着を縫った。
田植えは近所の娘さん達5,6人とバスに乗って行った。
新井柿崎線を長峰で降り、そこから上直海まで数キロ歩
いた。
田植えの身支度はピンクの腰巻きをしっかり付け、上から
新しい野良着を着て黄色の帯を締めた。
手甲、きゃはんをつけ、赤いタスキを掛け、手ぬぐいで顔を
覆いすげ笠を被ると身が引き締まり、晴れがましい気持ち
になった。
雨降りでは持参した箕をまとった。
男衆は苗の仕度をし、格子を置いて植える目安を付け、
植えるのはもっぱら早乙女の仕事だった。
午前午後の途中に休みがあり、お茶とともにボタ餅やキナ
コ餅などの甘くて美味しい食べ物が出された。
それらは大きな朴の葉にくるんで用意された。
お昼は足を洗って上がり、昼寝をしてから午後また植えた。
一日が終わった夕食に赤飯とともに、刺身や煮物に焼き魚
など贅沢なご馳走が振る舞われた。
行った農家で2晩ほど泊まったが、若かったせいか辛かっ
たり、腰が痛くなるなどの記憶はない。
こちらの田植えの時に、今度は行った先から娘さん達が来た。
彼女らを迎える前に、朴葉を取りに行くのは自分たちの仕事
だった。
(地元の娘さんと遠来の娘さんと一緒に田植えをするのかは
お聞きしていませんでした.。
両地を結ぶ親戚筋が早乙女の往来を「いっこう?」として取り
まとめているようでしたが、これも詳しくお聞きしていません)。
男衆が段取りをつけ娘さんたちがが本番の苗を植える。
お話から田植えは通常の農作業と異なり、豊作を願うハレ
の神事でもあり、産む能力を有した早乙女たちは田の神の
使者の役をも委ねられているように思われた。
お二人とも思い出しながら気持ちが昂揚されるのか、生き
生きと話してくださった。
昨今の社会は一見自由で便利だが何かに付け複雑で、自
身の立場や役割を明瞭に把握するのにしばし困難を伴う。
そのうえ人生は長く、存在理由の曖昧さはさらに広がろうと
している。
較べて昔の人の人生は短い。
それで農村などでは年令などに応じて立場、役割が適宜一
般化され諸般無駄の無いよう計られていた風に見えた。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。
- 雪と車 そして選挙。
- 直江津、無印良品で。
- 2月の好天、期日前投票。
- 新たな倉石隆作品「節句」。
- 本日誕生日だった。
- 最近の妻の料理から、夕食。
- 道路を歩く雌キジ三羽。
- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。
- 道路に出てくる野鳥。
- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。
- 長くなりそうな本物の大寒。
- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。
- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。
- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。
- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。
- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。
- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。
- 寒波前の冬鳥たち。
- 届いたサントリーフラワーズのお花。
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月









































