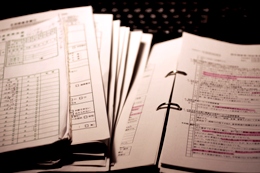医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
冬の来て道は喘ぎの場となりぬ
昨日、初雪らしく降った。ここ海岸線の降りは控えめだったが、行き交う人に難儀が見えた。
新潟県に住んでいると雪が降って初めて冬を実感する。今年は夏があれだけ暑かったので、冬はどれほど寒かろうと大雪を恐れている。
天気予報のせいもあって昨日の雪降りは会う人みな予想していた。一昨日、用事で妙高市へ行った妻も「こんなに温かいと明日は降る」と聞いて帰ってきたばかりだった。
長めの予報では前半は例年並みという。しかし例年並みの内容がよく分からない。これまで思ってもみない暖かな日に恵まれていた分しっぺ返しがあるのでは、と疑心暗鬼で空を見る毎日。冬将軍という影の如き存在を思い浮かべながら、善人であれば、とつい期待をしてしまう。
樹下美術館の駐車場はスタッフが雪かきして確保しています。この程度ならカフェの雪景色は貴重な眺めだと思われます。
冬の来て道は喘ぎの場となりぬ 雪なき国の人は知らずや sousi
ようやく猛暑の影響が収まりつつあり、そして園児の健診
10月も半ばになってようやく猛暑の健康被害に終止符が打たれようとしている。今夏の状況を振り返ってみた。
●脱水症単独および高熱や化器症状などの合併21人。
●暑さによる血液濃縮の影響が想定された心筋梗塞1人、虚血性腸炎1人、脳梗塞1人。
●胃潰瘍に暑さストレスが関係したと考えられる吐血1人。
●高熱を伴う尿路感染症3人
※暑さとの関連は不明だが、普段あまり見ない亜急性甲状腺炎2人。
年齢は20代から90代までさまざま。しかし高齢者に重症が多かった。多くは点滴が必要であり、血管合併症のあった方など5人が入院。高齢のお一人が亡くなられた。
丸二ヶ月、重い尿路感染症の消長を繰り返した在宅患者さんお二人は、今週になってようやくお元気になってきた。一時期高熱とともに炎症指標であるCRPが15~20以上へ上昇、お一人の白血球は2万を越えていた。
ご家族は一貫して家で直したいと仰られ、日曜祝日も補液と抗生剤の点滴に通った。こんなにひどい夏は初めてだったが、新たなノウハウも少々得た。
さて昨日午後は保育園の健診。生後4ヶ月の幼い赤ちゃんがいることに驚いた。園児は2,3才から自分の顔が出来てくる。ああ、このような顔でそれぞれの人生に臨むのだ、皆がんばれと心でエールを送った。
途中、身体の不自由なお子さんがしくしく泣き出した。すると子どもたちが次々と集まってきて、頬や頭を撫でた。平和なやりとりに心和んだ。そうかと思うと並んでいた女の子がいきなり男の子を突き飛ばした。びっくりしたがすぐ平静にもどっていた。愛らしいミニチュア社会、保育園。皆さんの肺も心臓も元気だった。
草々の闇にこだます歌の主 一寸の体(テイ)五分の魂
午後から夕刻には降るという予報。当てにならないとみて芝に水遣りをした。一時間ちょっと、全て着替えるほど汗をかいた。
いずれ涼しくなろうし、3ヶ月もすれば大雪におびえることもあろう。知ってはいても大愚痴を言ってしまう今日の暑さだった。
水遣りの庭の終わりは一斉に虫の音。思えば一様な虫の音も一命ずつの魂の歌にちがいない。今はどうしても一様に聞こえるが、こおろぎの頃にはそれがよく分かる。
今日の本業で比較的若いボイラーマンが吐血でこられた。原因は服薬中断の胃潰瘍。積もった暑さ疲労もあったことだろう。ほかにショート利用中のお二人の老人が高熱のため無念の帰宅をされた。
明日、日曜も在宅患者さんの点滴に回る。このままだと暑さの影響が蓄積されるこれからが本番の危惧もある。病院も手一杯だろう、まさに災害の様相だ。
最後が大変だった九州一周旅行、そして南国情話
昭和43、4年の昔、まだ駆け出しのころの夏、団体による九州一周旅行の医療斑のアルバイトがあった。
行程はきつく、一泊目は夜行寝台、途中2泊を湯の児と阿蘇に泊まって、最後の夜は別府ー神戸の深夜の航路だ。
班と言えどもあとは看護師さんだけ。その看護師さんは吐きそうな人を看ると自分が先に吐くような人で、少々心配だった。
一行は少なくとも10台のバスを連ねる教師の団体旅行。何度かタクシーで最後尾に付くことがあった。しばしばクーラーの故障によって長い車列が止まった。草原で止まった時など、西部劇の幌馬車隊を彷彿とさせた。
連日早朝からの強行軍で朝が苦手な私は車中眠ってばかりいた。目的地ではガイドさんの案内を聞きながらひたすら歩いた。長崎平和公園、湯の児温泉、阿蘇、磯庭園、シラス大地などを覚えている。一団の皆さんは毎日お元気だった。
比較的平穏な道中の最後に思わぬ修羅場が待っていた。別府で盛大な夕食をしてから乗ったのは、大きな船だった。玄界灘を通過して瀬戸内海へ入る航路で、朝焼けを楽しみに寝付いた。
しかしそれが暗転してしまう。深夜を過ぎて突然腹痛や嘔吐が一行を襲った。
驚くほど多くの人が床の上で苦しんだ。早々に青くなった看護師さんもなんとか一緒に船内を飛び回ってくれた。食中毒が心配された。
めいっぱい用意していた注射薬を大方使い果たして神戸港に着いた。下船後、岸壁で海へ吐く人が何人もいた。幸いなことに上陸してから次第に落ち着きはじめ、数時間後にはポートタワーの観光もこなして新幹線の帰路についた。病に加え、人の強靱さも見る思いだった。
部分的な潮流の変化がもたらした船酔いだったのだろうか、今でも判然としない。
慌ただしい旅の中で南国情話が懐かしい。タクシーの運転手さんが道中塩カラい声で歌ってくれた。何度も聴いて一緒に歌った。唯一の旅情はこの歌だったかもしれない。
家族や個人的な旅行が中心の今、あのような団体旅行はどうなったのだろう。
入道雲と夕焼け、そして異常熱波の影響
夕暮れ時、樹下美術館のデッキからむくむくとした入道雲が見えた。雲は妙高山をすっぽり包み、そちらでは雨が降ったのだろうか。雲の見える所は涼しげに見えて羨ましい。
近くの潟川は童話的な夕焼けだった。直江津の関川河口などでは壮大な夕景が見られたかもしれない。
仕事方面で異常な熱波の影響が続いている。
昨日、今日と点滴をした方はまだ若い。一昨日午前、数時間の草刈りのあと焼却作業をしたという。昼食後急に変調して発熱され、この方も炎症反応が亢進していた。また本日の屋根職人さんもきわどかった。
疲労がかさみ、屋外労働の状況は深刻さを増している。ほかに生徒の部活そして甲子園。いずれも厳重な監視が求められ現実的な制限が必要になるかもしれない。
新潟県立柿崎病院、そして高岡から
今日は上越市柿崎区で新潟県立柿崎病院主催「頸北地方の医療を考える会」に参加した。あまつさえシンポジウムの一番バッターを指名されてかなり緊張した。
同病院のこころざし熱き藤森院長の総合司会のもと、自治医科大学地域医療学センター長・梶井先生の基調講演で開会した。
柿崎病院は明治17年来の歴史があり、地元で長く愛された病院だ。55床の小病院ながら、日ごろ在宅医療を始め呼吸器など色々お世話になっている。
同病院には民間の後援会があったり、地元による心づくしの財政支援システムがあるなど、如何にも地元密着の実績がある。今日不肖私は、同病院の概念を「地域密着医療」から進めて「地域愛着医療」の実践病院と表現させていただいた。
振り返れば、梶井センター長には上越医師会役員の折り、上越地域医療センター病院の医師招聘の相談で何度かおお目に掛かったことがあった。今日は懐かしい先生と、懇親までご一緒させていただいて光栄だった。
「みんなの医療」、「知恵と工夫」、「人生はどこかで鐘が鳴る、しかもその兆しも現れる」、「教えることはできないが、伝えることはできる」、、、。梶井先生の医療と人生のしずくに触れて感銘を受けた。
さらに今日の会で小さきことも良きこと、の実感を得た。あらためて小さな樹下美術館に希望の灯を点させてもらった。
会を終えて帰宅すると、先日、富山県高岡市から来館されたご家族が、今日再び樹下美術館を訪ねて下さったことを知らされた。何ともいえない幸せを感じた。
明日は同業者のゴルフコンペ。腕は磨かずとも靴を磨いて参加しようと思う。

樹下美術館の庭
チマキ
午後、お年寄りの急な腰痛を往診した。骨折でなくてほっとした。
大おおおばあちゃんの診察を終えると、年配のご夫婦はちまき作りに戻られた。奥さんが笹にお米を詰め、ご主人が巻いていく。近くの作業所で出荷用を作り、家では自分たちのを作るという。
立派な笹が使われていた。銅鍋で煮ると笹の色が青いまま褪せないと聞いた。見てると呼吸のあった仕事ぶり、出来たらお持ちしますと仰ってくださった。
これからの季節、梅雨空とチマキはうるわしい田舎の風物詩だ。お宅のまわりの田んぼがいよいよ生気を増していた。
その昔、アカシアの花などを食べようとした私たち。後によそからチマキを頂くことがあった。砂糖入りのきな粉を付けて、あまりの美味しさに頭がヘンになりそうだった。
貴重な明治生まれ
美術館たる者、たとえ小館であっても図録一冊出せなくてそれとは言えない。このところ決めた期限が迫って懸案の制作に追われる毎日となった。いつしか大小400点に迫った分量もあるが、日頃の整理の甘さを痛感させられている。
それで毎日のように明け方まで格闘が続く。若ければもっとはかどるのに、一日は35時間くらい、一ヶ月は45日くらい欲しい、など考えるまでになった。それに何とかノートも、、、。
さて一先ず色々置いて、私が在宅でフォローしている方に明治生まれの人が4人いらっしゃる。いずれも女性でそのうち3人は100才を越えられた。4人のうち3人の方が杖で室内を歩行され、デイサービスへも通われる。お一人は押し車を使って近隣を散歩される。
残念ながら今日訪ねた方は骨折後に寝たきりとなられた。よくうとうとされているが、私たちが訪ねると一転して言語が冴える。今日の話をつないでみると次ぎのようになった。
「おや先生、相変わらず惚れ惚れするようないい男ですねえ。私がもっと若ければ本当に惚れるところですよ。
これでも学校時代の私は飛び競争の選手で、試合で直江津や柿崎までよーく歩いて行ったもんです。マイクロバスなんて無かったですから。
その時の先生がまたいい男で、私を好きだったらしいです。しかし私はまだ若かったからそんなことは分からなかったんです。今なら惚れるのに残念だったですよ、本当に。 しかし先生は男前だ、お帰りは気をつけて!先生もお元気で!」
すらりとして長身、言葉もきれいで、いつも似たようなことを仰る。要は褒めてやるからさっさと用事を済ませて帰りなさい、という風にも聞こえて、さすがだと思う。
よく面倒を見られている息子さんと、同行の看護師がくすくす笑いながら聞いている。
今日は明治生まれの女性から多めに褒められて疲れが和らいだ。それにしても彼女たちの存在は非常に貴重だ。お会いしてお話できるのを幸せに思う。
 |
 |
| 樹下美術館隣接の庭のミヤコワスレ | 同じにヒメサユリ(乙女百合) |
この雨は嫁の涙か介護の家
連日冷たい雨に降られている。
先週、今週と在宅介護が始まったばかりのお宅への訪問があった。「大変ですね」とお嫁さんに声を掛けると、わかりますか、と言って二人とも突然ぽろぽろと涙をこぼされた。時と場所が違う二人に同じ涙。
先週のお宅ではおばあさんの足が不自由になって失禁も頻繁に始まった。しかしどうしても私にオムツを替えさせてくれない、とお嫁さん。下着や蒲団が汚れていると思ったら、あっという間にいくつも褥瘡が出来てしまった、と。
そして昨日のお宅では、おばあさんの認知症の様子を話しているお嫁さんが言葉に詰まった。「おばあちゃん自身、親の介護などほとんどしなかったのに、貴方にはああしろ、こうしろと言うのでは」、と話してみた。みるみるお嫁さんの眼が真っ赤になって涙がこぼれた。
しばしば介護の家でお嫁さんたちは涙をこらえている。始まったばかりではなおさらだろう。しかしもう一人辛い人がいるのだ。不自由になったご本人(おばあさんたち)だ。この認識は円滑な介護のためにとても大切だ。私たちは常に二人のバランスを考え、当事者たちがうまく近づき合うように配慮しなければならない。
全ては 「困ったことがあったらケアマネや私たちに何でも相談してください」としっかり告げることから始まる。最初のお宅にヘルパーさんが、次いで介護ベッドが入り、大至急で訪問看護が始まった。昨日そのお嫁さんが薬を取りに来られた。
「私にもオムツを替えさせてくれるようになりました」とお嫁さんの少々ほっとした顔。
「何かと便利になりましたが、お金が掛かるのも事実ですね」と私。
「本当にその通りです」
「しかし、オムツを替えれば床ずれはどんどん直りますから訪問看護は早めに終るでしょう、あせらないで」と足した。
いずれの介護も始まったばかり、これからも色々なことがあると思う。しかしどんな事態にも方法はあろう。私も精一杯支えたいと思う。特に始まりでは話を聞いて、時には涙してもらうのも私たちの立場かもしれない。
忙しさ
美術館を営んでいると私のことをヒマな人と思われるかも知れません。しかし自ら言うのも恥ずかしいのですが、何かと本業(診療所)も忙しくしています。ちなみに昨日を振り返ってみました。
●午前の外来は40人ほどの診察。この間に心臓症状があって心電図に異常が見られた方を病院循環器科へ、またレントゲンに異常はなかったものの約一ヶ月カラ咳が続いている方を病院呼吸器科へそれぞれ紹介状を書いた。ほかに施設リハビリを受ける方の書類を終える。
※専門科への紹介は診療所の大切な役割だと思っています。
●昼近くになって、脳血管障害と認知症で長く在宅療養を続けられた方の急変の電話。緊急往診をしたが、処置の施しようがなく看取りとなって診断書を書いた。息子さんご夫婦は熱心な介護を続けられた。日中の看取りはあまり経験がない。
●午後から小学校で健康診断、150人ほどを診た。本日も続きがある。
●帰ってから在宅患者さんの往診と訪問で4カ所を回る。
●在宅まわりを終えて夕刻の診療。熱の下がらない旅行中の幼児を診た。インフルエンザとは考えにくかったが、昨年今頃の新型騒動が思い出された。明後日に帰る予定という、ぜひ元気になってほしい。
●午後7時から月一度の介護保険の要介護認定審査会へ。今回は20人分と少ないが100ページの資料を読み込んで臨む。3月にメンバーの組み替えがあったが、今回の委員もみないい人達だ。上越市には合計24チームの審査合議体があり、保健医療福祉の関係者144人が委員として参加し審査しています。
●審査会から帰ってから夕食(この間に妻は入所中の実家の母が痙攣を起こして施設へ呼ばれていた)。
●昼に要介護認定に必要な7件の医師意見書が新たに届いて12件となった。
忙しい日には「多くの人がもっと忙しくしているはず」などと思うようにしています。
(5月13日 木曜日 午前1時15分記載、すぐに寝なくては)
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。
- 頂いた椿を挿し木してみた。
- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。
- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。
- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。
- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。
- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。
- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。
- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。
- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。
- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。
- 週末の種々。
- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。
- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。
- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。
- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。
- 昨日レコード、今日白鳥。
- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。
- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。
- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月