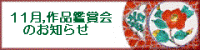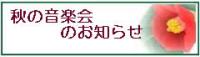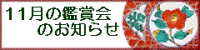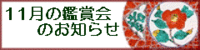花鳥・庭・生き物
1012年秋の庭で。
昨日は火曜日、樹下美術館の休館日だった。この日、春から委嘱されている特養ホームへ出かけた。
年のせいで、受け持ち31名の方のお顔と名が中々覚えられない。書類の作成や電話相談では不自由を感じるが、熱心なスタッフのお陰でなんとか勤めを果たしている。
帰りの美術館の庭は、ようやくホトトギスが賑やかになり、ノコンギクが咲き始めていた。これから沢山あるリンドウとリュウノウギクが咲く頃となった。秋の花は長いので助かる。
 ノコンギクにキタテハ |
 リストンボ
|
ホトトギスは本当に種類が多い。お客様に尋ねられることもあろう、花と名の整理を試みないといけないと思っている。
写真のリストンボは、翅先の茶の部分が広いのでアキアカネと異なるようだ。リスと言う人が発見したのでそう呼ばれるらしい。
ノートを書くようになって何かと身辺の興味が広がり、楽しい。
マリンホテルハマナスの雲 鳥は墜落しないが飛行機は墜ちる。
晴れると海へ行ってみる。大潟区四ツ屋浜、鵜の浜、柿崎区上下浜は仕事場から車で5分以内なので便利だ。
午後の雲が良かったので上下浜へ行った。腕はイマイチだが雲を背景にした丘のホテルは、やはりフォトジェニックだ。
間もなく頭上にトビがやってきた。トビはBlack Kiteといい、8月に撮影したミサゴはOsprayというようだ。

トビはBlack Kite。手のひらのように分かれた風切り羽が美しい。

今年8月、吉川区のミサゴ Ospray。急降下して獲物を捕るイメージから、物議をかもしている飛行機はオスプレイと名付けられている。
おそらく鳥は墜落などしないだろう。しかし誉れ高い先端文明の飛行機や原子力発電所は墜落や爆発を免れない。深刻な代償を内包するものを、発展や進化だと言うのは大丈夫なのだろうか。
台風一過 女郎蜘蛛の迅速な復旧作業。
17号台風が通過して二日目、ようやく雨が止み時折陽がさした。
仕事場の庭の一角で多くの女郎蜘蛛(ジョロウグモ)が巣を張っている。それが台風翌日に僅かの糸を残すのみとなっていたり、消えて無くなっているものもあった。
しかし、二日目の本日、あちこちに再び巣が張られた。真新しい巣は美しい工芸品のごとき輝きを放っていた。

これは台風のかなり前、9月10日に撮影した巣。すでに相当荒れた状態になっていた。

本日目にした出来たてピカピカの巣。真ん中に雌が陣取り、上方に小さな雄がいる。
女郎蜘蛛は主権在雌の世界。雌は上方に偏った円心部で巣を支配し、雄はさらに上の「蒲団部屋」のような粗末な場所に居候。ここで一世一代の交尾の機会をうかがう。

新しい巣は見る角度によって、黄色であることが分かる(大きくしてご覧下さい)。
ここにあった巣は台風によって完全に消失したが、本日見事に編み上がっていた。
蜘蛛の災害に対する迅速な復旧作業は、脱帽ものだ。
台風一過のスズメの群 見附市からのリピーターさん。
大型と伝えられて心配した台風は夜半にさっさと当地を通過したようだった。しかしさすがに、おびただしい枝や葉の散乱を残していた。
午後施設の仕事の帰りにスズメの群を見た。昨日の台風の一夜をどこで明かしたのか、雀たちは活発だった。自分の子ども時代に見た昔の群は、真っ黒と言えるほどびっしり鳥が木を占めていた。
家が近代化して、スズメの巣に不都合なこともなどもあって、個体数は減っているらしい。
新しい家でも軒に巣箱を取り付けるとスズメが入る。穴を小さくすること、頻繁に開け閉めをする場所を避けることが大切なようだ。
さて、本日雨降りの開館直後に見附市からご夫婦が来館された。齋藤三郎(陶齋)が大好きで既に何度かリピートされているとお聞きした。11月に筆者がご案内する鑑賞会にも来られるということ。喜び心からお待ち申し上げます。
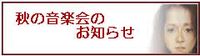
皆様による口コミとリピート。ささやかなカフェが付いた小さな常設展示館にとって、他に代え難い要点ではないかと思っています。樹下美術館の幸運をいつも感謝しています。
庭仕事 妙高山 お客様たち。
午後休診の木曜日、前回と同じように樹下美術館の草を取り、宿根草などを植えた。頂きものや仕事場からの移植などハナミョウガ、ハンゲショウ、ホオズキ、タムラソウ、それに赤い八重咲きのムクゲの苗が植わった。
知人の縁者で福島県を離れた方がおられ、育てていた山野草を頂いたので、それも植えた。ほかに従来のアヤメを倍くらいに株分けしてみた。どうか来年は沢山着いてもらいたい。

夕刻の買い物に出て見た妙高山と手前の南葉山。
山の重なり合いが壮大な空間を感じさせてくれる。
さて開館日の庭仕事はカフェなどのお客様から遠ざかった所をする。本日妻と作業(修行)をしていると、二組のお客様が庭に出られお話した。
お一人は近隣にiターンされた方。倉石隆の「秋」やカフェの図書、そして庭がお気に入りとて今年八回目のご来館とお聞きした。畑仕事は楽しく、自作の野菜ほど美味しいものはないと仰った。
もうひと方は横浜から長岡経由でこられたナイスミドルのカップルさん。かって写真で見た当館を気に入って訪ねてくださった。とても良いと言って頂き有り難かった。
樹下美術館は草花と同じく、人々が静かに混じり合うことがあって、張り合いを感じる。
夏のアザミから秋はタムラソウへ。
妻の知人からタムラソウの鉢を頂いた。お茶をされている方で花も上手に作られる。頂いた花もそそとして茶花の風情を漂わす。
私たちは庭に下ろして育てるので、大抵頂いたものより大振りになったり、暴れた感じになりやすい。
地に下ろしても肥料などあまり遣らず、どちらかというと雑草と混ざるようにするとよい、と聞いている。しかしこれがとても難しい。二株くらいに分けて場所を変えて移植し、また挑戦してみたい。、
 秋の花、タムラソウ。アザミを小ぶりにした感じで葉も小さくトゲは無い。
秋の花、タムラソウ。アザミを小ぶりにした感じで葉も小さくトゲは無い。
頂いた鉢の花は淡いピンクで愛らしい。
現在樹下美術館で展示中の齋藤三郎作品は四季の器です。秋の場所には、どんぐりの絵皿二枚、柿の鉢、赤かぶの大皿、柘榴の赤い掻落し壺などが並んでいます。
昨日は上越法人会のご婦人の団体様、本日は三条市と五泉市からお越しの方々、まことに有り難うございました。9月はさらにお客様で賑わっている印象があり、有り難く存じております。
上越市は米山水源カントリークラブ&ホテル、アイガモの給餌。
夕刻の外出は近くの米山水源カントリークラブへ。
そこの池で飼われているアイガモの夕食時で、スタッフが現れると鳥たちはお尻をふりふり後を追った。
食事は人の子どもなどよりよほど行儀良く、順に食べては交替した。スタッフはこまやかで、心なごむひと時だった。
家から10数分のゴルフ場。いま回数は減ったが、昭和40年ころ9ホールで開場していた前身時代から通った。すでにチャンピオンコースとなり隔世の感がある。
湖沼に面したコースの眺めは素晴らしく、水田の向こうに米山、尾神岳を望む四季は美しい。
遅く巣立ったスズメのヒナ。
さる8月28日に遅く巣立ったスズメのヒナのことを書かせて頂いた。今年巣立った若鳥たちはとっくに田んぼを謳歌している時期だった。厳しい残暑の中で巣立ちをした幼げな二羽のヒナの成長が心配だった。
しかし、その後の朝夕の庭に親子の鳴き声や姿が見られ、日中は静かになる日が続いていた。きっと三羽は朝田んぼへ出かけ、夕刻に帰る日課をしていることだろう、とひと安心していた。
本日夕刻、くだんの若鳥かなと思われた幼い鳴き声の個体が合歓の木に居た。まもなく一羽の若鳥と親が来て一緒に飛び去った。
今年早々と生まれた若鳥たちは成長し群を作り、ねぐらを拠点として生活しているはず。しかしこの二羽の若いスズメはまだ親と共に田と庭を往き来しているように見えている。
遅く生まれた代償として、ここに留まって親鳥と越冬し、来年テリトリーを分けてもらう仕組みを勝手に想像しているが、どうだろう?
もう20数年も昔の夏、負傷や落巣のスズメを育てた。試行錯誤を重ねると給餌を受けるようになり、屋内で私の足音や姿を追うようになった。数週間すると教えもしないのに用意した水や砂を浴びて驚かされた。
その後、広間で何日か飛翔の訓練らしきものをしたあと、試しに二階の窓から放った。一旦飛び出したものの、おびえたようにきびすを返して部屋に戻った。
こんなことを繰り返して数日、開けっ放しの窓から出て外で過ごし、餌を食べに部屋に戻るようになった。出入りの間隔が次第に長くなって一日数回から、さらに朝に出て夕方戻るようになった。一晩は家で過ごすのである。
ある一羽は、育ててひと月もするころ、朝早く寝ている私の髪を引っ張ったり、耳を突っついたりした。外には賑やかな若鳥たちの声がしている。庭へ出せとせがむ仕草であろうと考えて、窓を開けた。スズメは真っ直ぐ群へと向かった。
私には群に居てもくだんのヒナの声が分かった。飼い始めた当初、餌をねだって大声で鳴いたが、鳴かずとも餌をもらえる環境だったため次第に声が小さくなった。
啼くことと飛ぶことは鳥たる二つの証しである。小声を痛ましく思った。
ところで、かって部屋で餌を与える場合、小さな磁器の餌入れを耳かきで叩いて合図にしていた。放鳥後、庭に出て群に向かって器を叩いた。すると中から一羽が近くの枝に飛来し、さらに器に止まることを数回経験した。
当時鳥について、コンラート・ローレンツ博士の“ソロモンの指輪”で読んでいた。群から鳥が飛来した時、恍惚に似た幸福を味わった。
ある大雨の日、部屋に姿を見せず心配したことがあった。しかしその翌朝、軒下で啼いていた。窓を開けると部屋に入り慣れた高いスタンドに止まった。作った餌をついばみしばらくスタンドで佇むと、再び出て行った。
以後部屋に来ることも、庭で叩く器に反応する姿も見当たらなくなった。田んぼに稲が実る頃であった。群に同化してここを離れたのだろうと考えた。
くだんのスズメの頭には僅かのうぶ毛があるだけで頭髪がほとんど無かった。ある種障害があったかもしれない。しかし垣間見た独特の賢さによって、厳しい自然をも 生き抜くのではないかと、淡い期待をもって忘れるようにした。
しばらくの間、何かの拍子にあたりから小さなスズメの啼き声が聞こえると、姿を探してみた。
昭和60年前後によく問題のあるスズメの幼鳥に出遭った。ある日胸が裂けたスズメのヒナを拾った。手当をして鳥かご入れて軒に下げた。間もなく親が来て餌を与えたが、翌日には落鳥していた。また猫の多い場所に佇む飛べないヒナも極めて危険だった。
事故や負傷の幼鳥の飼育は保健所に事情を話し、叶えられれば経験者の助言のもと放鳥まで飼育を試みるのは有益だと考えられる。但し部屋のフンには少々の我慢が必要だ。
秋の初めの庭仕事。
夏の茂りにやつれが見える樹下美術館隣接の庭。雨が降ればまだ草も生える。
庭仕事は早起きしてすればいいのに、それが苦手なので大抵は閉館5時になったら始める。
本日は妻とともに草を取り、花木の枝葉を払い整えてみた。一時間半少々、夕刻とは言え風もなく蒸し暑くて大汗をかいた。
 南三陸町の山中で、弟は豚やニワトリの放し飼いをしている。
南三陸町の山中で、弟は豚やニワトリの放し飼いをしている。
彼のかく汗は私の何百何千倍だろう、などと思いながら終えた。
今年の庭仕事はもう一回同じようなことをやり、彼岸を過ぎたらいくつかの花や木を植えたり移したり、芝のはびこりを止め、全体に肥料を入れて終了。最後に待ち構える猛烈な落ち葉は、スタッフが頑張って掃いてくれるので助かる。
今年から私よりも妻のほうが熱心に手入れをする。朝は仕事場の庭もするので妻は少し腰が曲がってきた。
Early Autumn 樹下美術館にも初秋
ここへ来てやはり秋の訪れを感じる。
 午後4時半すぎの大潟区四ツ屋浜。直江津港を出た佐渡汽船が見える。
午後4時半すぎの大潟区四ツ屋浜。直江津港を出た佐渡汽船が見える。
You TubeにあったSoul FluitesのEarly Autumn
もう聴く道具はなくなったが、このレコードは今もケースにある。買ったのは医者になったばかりの1968年ころで、 Early Autumn はよく聴いた。くすぐったいような中低音のフルートのアンサンブル、響きのいいビブラフォンとリリカルなピアノが初秋の空気にピッタリだった。
当時長野県の小さな病院に一月ほど出張した冬、友人から借りたデッキでカセットテープにとって持って行った。
1975年に新潟県に帰って来てしばらくしてのこと、イタリア軒のラウンジピアニスト青木昌巳さんにEarly Autumnをリクエストをした。ややこしいコード進行をする曲を、ロマンティックに演奏をされたのはさすがだった。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。
- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。
- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。
- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天
- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。
- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。
- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。
- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。
- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。
- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。
- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」
- 長生きのお陰色々。
- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。
- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。
- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。
- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。
- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。
- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。
- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。
- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月