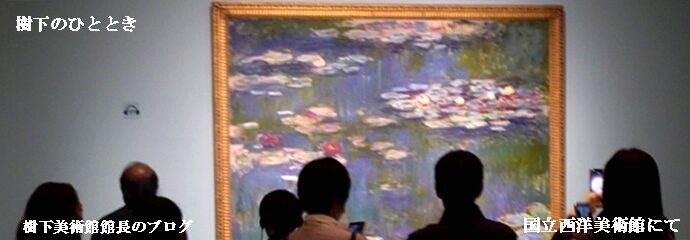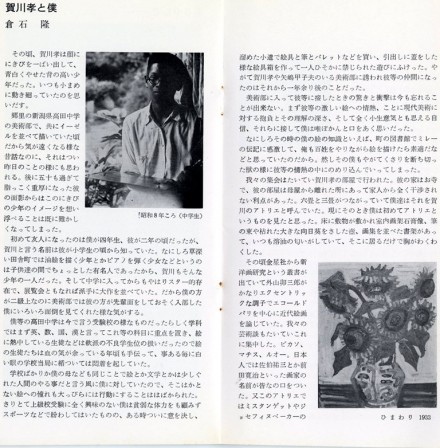花鳥・庭・生き物
本日の樹下美術館の庭 青鬼灯、クレマチス、葦、蟹そして桔梗。
暑さが一段落。樹下美術館の庭はテッポウユリが終わりアジサイは片隅に残るだけになりました。
そんな時期、桔梗が始まりました。
夕刻は、暑さにうなだれた福島県からのシラネアオイに寒冷紗を掛け、
水田に面した場所の葦(ヨシ)を整え、
花に侵食を試みる芝や、鋭いトゲをもつ周辺のワルナスビを抜きました。
 昨年初めて数株の鬼灯(ほおづき)を植えた。発芽後いつしか伸びてひっそり実を付けていた。
昨年初めて数株の鬼灯(ほおづき)を植えた。発芽後いつしか伸びてひっそり実を付けていた。
とても嬉しい。
 小生がこしらえた拙い竹の棚に一輪ずつクレマチスの名残花が続いている。
小生がこしらえた拙い竹の棚に一輪ずつクレマチスの名残花が続いている。
 水田に面した南側に涼しげな葦。
水田に面した南側に涼しげな葦。
夏の風情ですが、いずれ一気に群れますので本日少し抜きました。
甲羅が2㎝ほどのとても小さな蟹が突然現れました。  くびき野は稲穂のおほきく育つ日に 我いとちひさき蟹と戯る
くびき野は稲穂のおほきく育つ日に 我いとちひさき蟹と戯る
正面の顔は怖いのですが、甲羅は愛嬌がありました。
雨に香る百合。
7月の声を聞いて梅雨の本番となりました。樹下美術館の庭はアジサイから百合へと変わりつつあります。
夕刻の雨上がり、園内を歩いてみました。
 百合の香を残して雨の上がりたり
百合の香を残して雨の上がりたり
→百合の香を残して樹下の雨上がり
(最初があまりに良くないので7月5日に直しました。よみ人同じでは中身も同じ?)
忽然と消える不思議の鳥コムクドリの親子。
さて連日のコムクドリです。筆者は何度か彼らのことを〝不思議の鳥〟と呼ばせて頂きました。
詳しく観察していませんが、不思議とは次のようなことです。
①つがい以外のフリーな鳥たちの意味不明な関与。
②あっけない子育ての終了。
①について:巣にはしばしばつがいではない個体がやって来る。ヒナの巣立ちが近くなるとその数を増し何羽も来て巣を覗き、巣に入り、また賑やかに鳴きます。しかしいくら空腹のヒナが叫んでも餌は運びまんせんし、一体何しに来るのでしょう。
③ある日ヒナは身を乗り出して大声で叫び餌をせがむが、親鳥の姿は現れず、翌日にはヒナも消える。
この時期、家の周囲でスズメ、ツバメ、カラス、カワラヒワ、さらにムクドリまで、巣立ったヒナが親に給餌をせがむ姿が見られるようになります。しかしコムクドリは昨年同様、親子してあたりから忽然と消え去りました。〝飛ぶ鳥後を濁さず〟それにしてもその後ヒナはどうやって生きるのでしょうか。
 6月19日雨の中、空腹のヒナの前に盛んに現れるフリーの鳥。これはオス、餌は運ばない。
6月19日雨の中、空腹のヒナの前に盛んに現れるフリーの鳥。これはオス、餌は運ばない。
鳥の親はめいっぱい開かれたヒナの黄色のくちばしを見ると餌を与えずにはいられない、と云います。
ヨシキリの巣へのカッコウの託卵は、これを利用して行われています。
こんなにせがんでいるのに親でない鳥は全く餌を運ぶことはしないのです。自然界の遺伝子支配は絶対的であたかもパソコンのプログラムの如くです。
 同じ日、ただ来るだけのフリーのメス。この日親鳥の姿を見ることはなかった。
同じ日、ただ来るだけのフリーのメス。この日親鳥の姿を見ることはなかった。
フリーの鳥はもしかしたら巣離れを促しに来るのでしょうか。
 巣から実を乗り出すヒナ。巣立ちかもしれないが、飛翔をみる暇がなかった。
巣から実を乗り出すヒナ。巣立ちかもしれないが、飛翔をみる暇がなかった。
昨年と同じく、翌日20日に親子とも姿、気配が消えていました。
コムクドリはツバメと同じく南洋からの渡り鳥と云うことです。飛翔は実に滑らかで自在。様々な声色で鳴き、ヨシキリに劣らず饒舌でよく歌います。私は他で見かけず、ここの合歓木(ねむのき)だけで見るのも不思議だなと思っています。
現在、残ったフリーのオスが木に来て盛んに囀っています。ペアを探しテリトリーを主張しているようにも見えますが、この先どうなるのでしょうか。
さて、 今夕、食事前に寄ったゴルフ練習場(上越市下門前:ゴルフプラザ ビーボ)
今夕、食事前に寄ったゴルフ練習場(上越市下門前:ゴルフプラザ ビーボ)
明日は同業のゴルフコンペ。四月に50-51で優勝しました。ハンディキャップが34+2もあったのです。今度はで29+2です。
70才を過ぎると2がプラスされ、その上前のティーから打てます。前回はうっかりして皆さんと一緒にレギュラーティーで回りました。明日もそうするつもりです。
今年は出来るだけこの会に参加しようと考えています。良くても悪くても明日の成績はご報告したいと思います。
樹下美術館の庭にも夏は来ぬ 料理人も来られた 地域ケア会議。
本日見たもの出会った方たち。
本日、今秋予定の「陶齋の器で食事会」で包丁を振るわれる料理人さんがお見えになりました。食器や庭をご覧になり、大変楽しみと仰って頂き安心しました。
ところで食事会は詳しくお知らせする前に、ホームページ案内へのお問い合わせだけで既に満席となってしまいました(10月の毎週日曜正午、一回5~7名様の予定でした)。
今年うまく行きましたら来年の初夏にもと、考えておりますのでどうか宜しくお願い申し上げます。
話変わって今夕、上越市大潟区の地域ケア会議がありました。地域包括支援センター主催、各事業所ケアマネジャー、市担当者、医師らも加わり40名余が参加し、有意義でした。懇親会もあり、ひごろ公私とも如何に沢山の方のお世話になっているか、あらためて知る思いでした。
大潟区の良いところの一つは医師同士、自然で仲が良いことだと密かに思っています。
合歓木のドラマ コムクドリの〝つがい〟に半生が過ぎる。
仕事場の二階から見る庭の正面に合歓木(ネムノキ)の老木がある。以前に書かせて頂きましたが、筆者の父が往診帰りに林から採ってきて植えた木です。私の子どもの頃なので60年くらいは経っていて、かなりの部分が枯れ始めている。
木にはカラスやスズメの常連以外に7,8種類の鳥が寄る。昨年初めてその木の洞(うろ:枯れ木が落ちて出来た空洞)に、コムクドリのつがいが営巣してヒナをかえしたのを見た。
彼らの外見は珍しくオスメスの区別がはっきりしている。ズームで撮って拡大された様子などはいずれも変興味深かいものばかりだった。一連のことはブログのために買ったカメラのおかげ、いや、ブログのおかげで出会えた楽しみだと思っている。
コムクドリは渡り鳥で、昨年7月中旬、子育てが終ると全員があっという間に姿を消した。今年は運良く昨年よりおよそ3週間早く、4月23日から目にすることが出来た。当初以前のペアかと考えたが、今では翼や首筋の模様などから違うペアだと認識している。
さて春先、なんとも初々しい二羽は山桜で遊ぶなど新潟県は上越の春を謳歌するごとくだった。
 毛繕いする春先のメス 毛繕いする春先のメス |
 毛繕いする春先のオス 毛繕いする春先のオス |
4月下旬、同じ木の別の洞でスズメが巣作りをはじめていた。だがコムクドリはまだ花と遊ぶ風だった。
それが5月28日にはすでに抱卵が、6月3日ころには給餌の様子が観察された。つがいはわずが二ヶ月の間に、別人の如く逞しい親鳥へと変身している。(短時間に成長する彼らのことは昨年も書かせて頂きました)
 木の股にある洞へと餌を運ぶメス。 木の股にある洞へと餌を運ぶメス。 |
 同じくオス。 同じくオス。 |
洞を覗きに来るつがい以外の若鳥と考えられる鳥たち。 左オス、右メス。
左オス、右メス。
親鳥が餌を運び始めておよそ11日余。20メートル先の洞から聞こえるヒナの鳴き声が非常に大きくなった。すると昨年同様どこからともなくフリー?(独身)の若鳥たちが何羽も入れ替わり立ち替わりやって来て巣穴を覗いたり、大声で鳴き合うなど木が賑わう。あたかも巣立ちを促すようであり、祝福のようであり、学習のようであり、大いなるひやかしのようでもある。
彼らはしばば巣に出入りするが、決して餌を運ばない。あとはお互い追っかけっこが仕事で、飽きると飛び去る。
 昨日、何気なく撮影した写真。給餌に使われる大きな洞の下に今年出来た小さな洞から顔を出すヒナが。両者の巣穴は中で繋がっている。
昨日、何気なく撮影した写真。給餌に使われる大きな洞の下に今年出来た小さな洞から顔を出すヒナが。両者の巣穴は中で繋がっている。
飛来した個体はつがい以外の鳥で、ヒナが期待しても餌は運ばれない。巣のヒナが写ったのはこれが初めて。かなり感動した。
ところで以前、合歓木でどんなドラマが生まれるか楽しみ、と書きました。コムクドリは順調でしたが、同じ木の別の洞に営巣したスズメのペアはかなり悲壮な経過を辿っています。一度は巣作り、抱卵、給餌行動まで進みましたが、たびたびの妨害に遭い、給餌を中止し、巣作りからやり直しているのです。
妨害をしたのはこともあろうに別のコムクドリたちでした。妨害というより陵辱に近い行動で、あまりのことに驚きました。この先、スズメの営巣中断が危惧されます。スズメのことは今後また書かせて頂こうと思います。
長々と鳥のことで申し分けありません。
減量で昔の式服が楽に着られた 置いた水をコムクドリが飲んだ。
かって医師会長をしている時に葬儀や結婚式に参列する機会が多かった。甚だ不謹慎な話になるが、その時自分も含めて多くの参加者の式服がパンパンとして窮屈そうな事が多いのに気がついた。特に男性がそうだった。
そもそも式服は生涯に何度も新調するものではない。社会に出て一回、その後体型が変わって二回目などがせいぜいであろうか。
しかるに新調して5年、10年が経つと、次第に体重が増えるのもおよそ一般的であろう。それでいざ服を着る時、ダブルのボタンが止まらない、ジッパーに苦労し、袖も裾もツンツルテン。お腹をへこませて無理矢理着ると、黒は締まって見えるし、式はおごそか、それに紛れてなんとか形になろうか、というのが一般的だったようである。
このたびある方の「おとぎ」によばれた。これまでの式服は一苦労あった。しかし昨年11月来、食事を是正し階段昇降運動を続けると2月に9%近く体重が減った。その後リバウンドもなく、このたび服はすんなりと肩と乗り、ズボンはすっと気持ち良く入った。
職業がら皆様には適切な食事と運動、その結果の好ましい体重維持を勧めてきた。皆さんが懸命に付いて来られようとされるので、心こめて応援している。健康のほかに、昔の服がすっと着られるのも良い産物だとこのたび実感した。
ところで現在、仕事場の庭にある合歓(ねむ)の古木でコムクドリがヒナをかえし、懸命な餌運びを行っている。続く暑さを考えて地上2メートル巣の下1メートルほどの所に簡単な水場を取り付けた。
三日間、鳥は近づく気配を見せなかったが、本日一羽のメスが水を飲むのを見た。この鳥はツガイ以外の独身と想定される個体だった。動物世界で新しいことを始めるのはいずれも若い個体だと云う。
本日の記載を始めた午後11時20分、突然雨音がして降り始めたが、10分ほどで止んだ。もっと、もっと降ってくれないと!
夏の庭へ 賀川孝氏のご子息とお会いした。
午前に雨模様となったが庭や畑を潤すほどではなく、午後から晴れた。庭は勢いを増していて次々と初夏の花を点けていく。
紅白のキョウガノコ、白いアスチルベ、シモツケ、青いホタルブクロ、一番乗りしたホトトギスもあって賑やかだ。
本日は初めてのお客様も多くお見えで、皆様一様に展示をご覧になり、お茶を飲まれ庭を歩かれたようだ。樹下美術館は設計の途中カフェは無かったが併設して良かったと振り返っている。また好きな庭にも恵まれて幸せを感じる。
 本日も倉石氏ゆかりの方が東京からお見えになった。新潟県立旧高田中学校の同窓で、自由美術を経て主体美術協会の創始会員となられた同志的画友、賀川孝氏のご子息だった。
本日も倉石氏ゆかりの方が東京からお見えになった。新潟県立旧高田中学校の同窓で、自由美術を経て主体美術協会の創始会員となられた同志的画友、賀川孝氏のご子息だった。
賀川氏は帝国美術学校(現武蔵野美術大学)、倉石氏は太平洋美学校へと進んだ。後の日も、二人は取っ組み合いの喧嘩をするほどの友だったと云う。
氏は原始美術や民族芸術の原初的な普遍性を追求されていた。残念なことに比較的お若くして亡くなられ、倉石氏が追悼文を書いた。
お会いしてご子息は年経るにつれ父を好きになった、と仰った。このたびは自らのルーツを訪ね、上越高田から樹下美術館へと回って来られた。
私も両親については同じような経緯がある。特に亡くしてからは、両親と一体化しているような感覚さえ時にある。本日訪ねて来られた氏から似たようなお話を聞きながら胸熱くなるのを覚えた。CGアートと取り組まれている氏、またお目に掛かりたいと思った。
※6月9日の追加・以下は冊子「賀川孝遺作展」(1979年12月/東京都京橋「ギャラリーくぼた」)に寄せられた倉石隆の追悼文の一部です。全19ページの中に小田嶽夫氏の寄稿も収められています。
撒水の午後。
本日は日曜日.。数日お天気が続いている。雨が少なく、庭が乾いているので午後遅く出かけみっちり撒水をした。
それから混み始めた椿やモミジの枝を払い、やって来た妻と裏手の雑草を取った。7時過ぎまで2時間少々、ずいぶんすっきりした感じになった。
 ジャックランドの「眺めの良いカフェ特集」で紹介されたせいか、昼を中心にご家族づれや若い人たちで賑わったと云う。
ジャックランドの「眺めの良いカフェ特集」で紹介されたせいか、昼を中心にご家族づれや若い人たちで賑わったと云う。
夕刻近いカフェはとても若いカップルが見えていて楽しそうに本などを開いていた。 挨拶した後、邪魔をしないように通路のテーブルでロールケーキを薄くカットしてもらい、リモージュのデミタスカップで珈琲を飲んだ。人が通る所だが、この席で少しだけお茶を飲むのも楽しい。
 芝は旺盛に成長している。間もなく今年初めての芝刈りとなる。いよいよ夏、まだ梅雨の気配もなくとても良い気候だ。
芝は旺盛に成長している。間もなく今年初めての芝刈りとなる。いよいよ夏、まだ梅雨の気配もなくとても良い気候だ。
古流松應会、深雪支部の花展 町の活性化。
午後、古流松應会、深雪支部の花展に行ってきた。伝統の生花(せいか)、創意の自由花、一生懸命な作品はそれぞれとても魅力的だった。
 生花 生花 自由花 自由花  自由花 自由花 自由花 自由花 |
 自由花 自由花 自由花 自由花 生花 生花 生花 生花 |
開場は、あすとぴあ高田のミュゼ雪子町5Fだった。立体駐車場の出入りは余裕があり楽に感じられる。花展はとても賑わっていた。5年に1度の作品展と聞いたが皆様には大変なご苦労だったことだろう。
こどもの作品コーナーがありなかなか楽しかった。「私もやってみたい」というお子さんの声が聞こえていた。
●開催は3日(月曜日)午後6時まで。
イレブンプラザへも寄った。駐車場に車は少なかったが、歩いて入る人がかなりいるようだ。せっかくの本町通り、普段はその方が合っているかもしれない。
目薬とガムを買って活性化に協力した。それにしても「町(地域)の活性化」は下手をすると「沈滞」の裏の顔を思い出させる。それで活性化と聞くと少々気が沈み、そこを避けたい気持ちがしないでもない。黙って努力を重ねる方が遙かに魅力的なのに。
活性化は「やっています」、という一種アリバイ的な行政用語から発しているかもしれない、しかしどこか寂しい。京都も長崎も、日本中が活性化を叫んでいるらしい。補助事業ゆえであろうが、名勝地への夢がしぼむ。もう十分であろう。ここまで来たら特に商業地や観光地は、あまり活性化と言わないほうがいいのでは。
小雨の庭 穏やかな夕やけ。
風邪気味が続いていたので休診の午後にぐっすり昼寝をした。気持ちよく目覚め、樹下美術館へ行った。
小雨の美術館は静かでお二人の若いお客様、雨の庭もいいですね、と仰った。
明日は晴れる予報が出ていた。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 週末の種々。
- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。
- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。
- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。
- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。
- 昨日レコード、今日白鳥。
- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。
- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。
- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。
- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天
- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。
- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。
- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。
- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。
- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。
- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。
- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」
- 長生きのお陰色々。
- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。
- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月