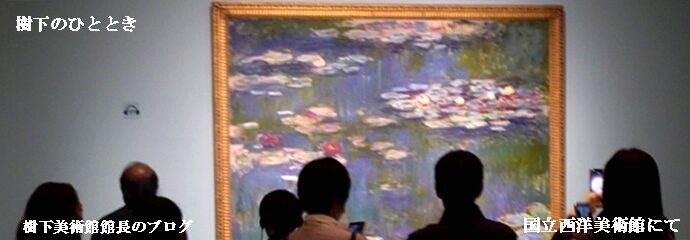花鳥・庭・生き物
風が残った日。
日中、昨日吹き残した風が止まなかった。
本日は概ね空の半分ほど青空が見えたが、雲は忙しそうだった。
 3軒の在宅回りの水田地帯、いつしか沢山の雁類が来ている。
3軒の在宅回りの水田地帯、いつしか沢山の雁類が来ている。
元気な冬鳥を見ていると「寒い」と言うのに気が引ける。
 雲間からいたずらんぼのような月が覗いていた。
雲間からいたずらんぼのような月が覗いていた。
6日が満月らしい。晴れてくれないかな。
夕刻ようやく風の音が止んだ。
鳥にも好かれる樹下美術館。
先日二日続けて掲載しましたカフェ右側のモミジがほぼ落葉し終わりました。
男性スタッフによる庭木の雪囲いが終わり、残っていたこのモミジは特別に支柱を立て枝を釣るいわゆる雪づりで冬に備えることにしたそうです。
雪づりは格好よく風情もありますのでご欄になってください。
ところでこの樹のすぐ近くのモミジにも巣がありました。
いずれも建物に近く、しかもそう高くない場所で、かなり人通りもありますので驚きました。
私たちが行ったり来たりしていた頭上で鳥が巣を作り、産卵しヒナをかえしていたのですね。
それはどんな鳥だったのでしょう?
樹下美術館では毎年カフェの左上の軒下に雀が、庭の奥の巣箱にシジュウカラが営巣します。
当館が鳥たちにも気に入られていること、とても嬉しく思います。
枯れ芝を染めていくモミジ。
吹かれて散り、晴れても落ちた木の葉。
大方裸木となった庭で、カフェの右手で燃えていたモミジが散り始めた。
毎日掃いてきれいになった枯れ芝を最後のモミジが染めていく。
「しばらくそっとしておいて」と本日スタッフに言いました。
エラ・フィッツジェラルドの「木の葉の子守歌」
本日ご来館の皆様、大変有り難うございました。
本日で長かった旧歴9月が終わる 晩秋の田を被う蜘蛛の糸。
旧歴の話で恐縮ですが、本日11月21日が閏(うるう)九月の末日、長い秋がようやく終わります。
九月がふた月続き、十三夜の名月が二度あった閏9月は1843年以来171年ぶりということでした。
次にこの年が来るのは95年後の2109年だそうで、奇妙な時間感覚に包まれます。
このことで言いますと、以前上京日記で書きました小生の高祖父・玄作(1818-1874年)は25才の時に閏9月を経験したと考えられます。
「ああようやく9月が終わる、長かったなー」などと言ったかもしれません。
その後の閏九月は171年経った今年で、偶々不肖小生が迎えました。
玄作爺さんが〝どんな人間が次の閏9月を迎えるのだろう〟と考えたとしますと、私などで良かったのか心配です。
では私の子孫のどんな子が95年後次の閏九月を迎えるのでしょう。
少なくとも2~3代先までかかるかもしれません。
はたしてそれまで私の子孫と名乗る者が繋がっているかどうか。
その前に日本が無事立国しているかが問題、などということだけは無しにして頂きたいのです。
さて以下は昨日の当館のモミジです(まだ紅葉が目立つ木を残して雪囲いが始まりました)。
今年の当館の紅葉は例年よりもきれいだったようです。
ところで昨日頸城区で白鳥を見た田んぼは、一面細かい蜘蛛の糸のようなもので覆われていました。
このような景観を初めて見たのですが、やはり糸は蜘蛛のものらしいのです。
ある蜘蛛は晩秋の小春日和や春先の良い日に、空中に糸を飛ばす生活史があるそうです。
飛ばした糸が風に乗ると自らもそれと一緒に運ばれ、遠くで新たな生活をするということのようのです。
目にした糸はこのことと関係があるように思われました。
風が弱いためく舞い上がらずに田んぼを被っているのかもしれません。
農家の方や昆虫に詳しい人にもう少し聞いてみたいところです。
 本日の田んぼと蜘蛛の糸。
本日の田んぼと蜘蛛の糸。
ひこばえがあり、水がひたっている一部の田んぼで見られるようでした。
この糸は弱くて、産卵する赤とんぼが触れも平気でした。
晩秋の風物詩とし、糸がが飛ぶのを「雪迎え」と言う地方がある模様です。
夕刻のほくほく線 金色のたんぼと白鳥。
やっと晴れた晩秋の日、午後休診日だが施設のインフルエンザワクチンの接種があった。
それを終えて美術館のカフェへで、常連さんと沢山話した。
その後ほくほく線の電車を撮りに近くの田圃へ。
白鳥の群がいたので電車を入れようとするが中々難しい。
ところでよく見ると田圃は一面に細い蜘蛛の糸のようなものが掛かっていた。
落日が迫るとそれが金色に光った。
 名残惜しいほくほく線特急「はくたか」と白鳥の群。
名残惜しいほくほく線特急「はくたか」と白鳥の群。
 刈り穂の田一面に非常に細い糸が張り巡らされていて、陽を浴びると光る。
刈り穂の田一面に非常に細い糸が張り巡らされていて、陽を浴びると光る。
蜘蛛の巣であろうか、獲物は何だろう、とにかく初めて目にした。
 逆光の白鳥たちは波の上にいるようであるが、光っているのは蜘蛛の糸。
逆光の白鳥たちは波の上にいるようであるが、光っているのは蜘蛛の糸。
もう数日は晴れるらしく何より有り難い。
波浪と時雨とヤブコウジ。
連日の季節風は台風並み、というより当地では台風以上の強さ。
叩くような時雨(しぐれ)も容赦ない。
いっとき、あられも混じったという。
庭の傍らのヤブコウジはほっぺを真っ赤にして集まり、
固い葉っぱを傘にかかげ身を寄せ合い、吹き寄せる枯葉を抱えて暖まる様子です。
 真っ赤な実を沢山付けていた先日の樹下美術館のヤブコウジ。
真っ赤な実を沢山付けていた先日の樹下美術館のヤブコウジ。
今年は例年より実が多いと思われます。
わずか15~20㎝ほどの背丈ですが、草ではなく樹木なのですね。
荒れる空の下、こびとのようなヤブコウジたちは怠りなく冬仕度です。
明日はいよいよ蓄音機によるレコードコンサート。悪天候かもしれませんが、会場は皆様の熱気で暖かくなることでしょう。
イタヤカエデを植えた 何かを育てるのは張り合い、あるいは本能。
昨日11日は火曜日で樹下美術館は休館でした。
先日記載しましたイタヤカエデが年々立派になるのを見て、あと二本はほしいと考えていました。
さいわいネットの通販に1,5jメートルの苗が出ていましたのでそれを求め、
昨日お天気だった休館日に植えたという訳です。
 二本目は美術館左脇、もともと黄色のまだ幼いモミジがあった所を選びました。
二本目は美術館左脇、もともと黄色のまだ幼いモミジがあった所を選びました。
イタヤカエデはしばらくすると1年に1メートル近く伸びるようになりますので楽しみです。
 その小さなモミジを美術館の真裏、館内の細いスリットから見える所に移しました。
その小さなモミジを美術館の真裏、館内の細いスリットから見える所に移しました。
(いずれも支柱をもっと丈夫にしたいところです)
ところで70才を何年か過ぎて樹を植えるのでは、その成長を見る時間はたいしたものてはありませんね。
しかし一般に花や野菜、稻や樹、人や仕事あるいは趣味など、わずかでも何かを育てたい、という心境は年と無関係のはりあいで、
ある主本能の如きものではないかと感じられるのです。
かなり昔のことですが、長くお孫さんのお弁当を作っていた高齢のおばあちゃんがいました。
お孫さんは高校卒業後、都会の大学へ進学しました。
するとおばあちゃんに明らかな鬱が現れて進行したのです。
大学に受かったのだから喜べばいい、と家族は慰めましたが、最後は肺炎で亡くなられました。
日中お天気は持ちましたが、夜に入り予報通り風が強くなってきました。
日が短くなって 貴重な立ち話 今年の月。
私の定時在宅回りや往診は午後3時を過ぎて始まる。
この数年、一回2~4軒を訪ねる。
それ以前では3~5軒あるいはそれ以上だった。
夏場の午後3時はまだ強い日射しが残っていたが、今その時間は夕刻の色を帯びる。
少々不思議な事に、この時間帯に道路で立ち話をする女性たち(奥さんたち)を時々見かける。
私たちの出がけにそのような女性がいるとすると、
一通りの往診回診を終えた帰り道、同じ場所で同じ人がまだ話し込んでいることがある。
長い時には30分から小一時間が経っている。
しかも話している人の顔は大抵真剣だ。
「あっ、始まっている」と後ろに乗っている看護師に言うと、
「ほんとですねアハハ」と笑う。
長い立ち話は女として理解できなくもない、とも。
本日もそんな光景を見た。
既に4時に近くであり、あたりは暗くなっている。
よほど大切な話なのだろう、と思ってしまう。
ところで、かって家の近くで母が立ち話をしているのを聞いたことがあった。
「それではまた」
長い話がようやく終わるかに見えたその時、
「ああ、そうそうこの間の○○」と言った途端、そこからまた延々と始まった。
声を出すことは心肺機能が強化されることでもあり、長く話すのはランニングに似てなくもない。
ならばおしゃべりはストレス解消に役立つほか、身体機能の維持強化に繋がっている可能性を否定できない。
これが長生きの一因ならば羨ましいことである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年の秋はスーパームーンやミラクルムーンがあり月と良縁の年だった。
二回とも晴れて幸運といえよう。
今年は旧歴でいえば9月が一回多く、うるう9月は新暦の11月21日まで続く。
こんなことは今世紀中にもう起きないということだ。
私の年午年(うまどし)も残り少なくなったが、色々な意味で変わった年だったことになるのか。
紅葉のイタヤカエデとメグスリノキ。
二日続いた雨の後、三日続きの晴れとなりました。
日中温かく、午後在宅回りの車外気温は19℃を示していました。
お天気なのに風邪気味という方が増えているように感じられます。
さて先日紅葉のマユミとニシキギを掲載させて頂きました。
本日はイタヤカエデとメグスリノキを載せました。
イタヤカエデは御存知の方も多いと思いますが、大きな葉と鮮やかな黄色の紅葉が美しい樹です。
カフェの正面に植えて5,6年経ちますが、真っ直ぐ延びて既に5メートルはあるでしょうか。
メグスリノキは比較的珍しい樹木だと思われます。
現在二本ありますが一本は上越市清里区の造園業・丸山隆光園の亡き親方が20年前に植栽されました。
 右の黄色がイタヤカエデ、左の上半分がメグスリノキ(こちらはまだ8年目)。
右の黄色がイタヤカエデ、左の上半分がメグスリノキ(こちらはまだ8年目)。
 黄緑、ピンク、オレンジが華やかに混じるメグスリノキの紅葉。
黄緑、ピンク、オレンジが華やかに混じるメグスリノキの紅葉。
こちらは20年ほど経ったもの。カフェから見て左奥の方にあります。
メグスリノキの樹皮を煎じたものは眼に良いと言われ、さらに肝臓にもということで茶として販売されているようです。
別名「長者の木」とか「千里眼の木」などと呼ばれ、縁起の良さが感じられます。
美術館の庭は名園というほどではありませんが、秋の見頃になりました。
本日は晴天なり 庭の除草。
雨に降られた連休があけて本日は定期休刊日、そして晴天だった。
晴天と言えば、
「あ、あ、あー、本日は晴天なり、本日は晴天なりー、後ろOKですかー」
昔からマイクテストの際、雨の日でも「晴天なり」が使われている(と思う)。
もとは英語圏の通信テストで「It is fine today」が用いられてるのを、そのまま訳して日本で使ったらしい。
It is fine todayには発音の要素がうまく網羅されているため実用されたということだ。
しかし「本日は晴天なり」はただの転用であり、テスト向きに考えられていないという意見もあるようだ。
だが「今日は良い天気です」と口語になれば子音が乏しくてしゃんとしない。
「本日は晴天なり」は公式な電波テストで用いる言葉として長く法で定められているらしい。
今日様々なイベントのマイクテストで、
「あ、あ、あー」のあと、「本日は晴天なり、本日は晴天なり」と滑舌よく繰り返される。
その昔皆で芝居をした時、それこそ雨の日も真剣に「本日は晴天なり」と言ったのを思い出す。
(もう古い、今は言わない、ということでしたらどうかご容赦ください)
 本日午後の除草作業。
本日午後の除草作業。
余計なススキの株を掘ったり、ばらけたアヤメを切ったり、面倒な場所の雑草を取った。
全て来年のためであり、越冬する雑草取りや施肥など沢山仕事がある。
明日また晴れますように。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 週末の種々。
- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。
- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。
- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。
- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。
- 昨日レコード、今日白鳥。
- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。
- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。
- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。
- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天
- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。
- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。
- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。
- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。
- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。
- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。
- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」
- 長生きのお陰色々。
- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。
- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月