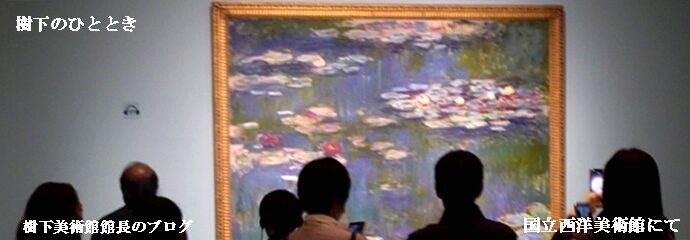花鳥・庭・生き物
草取り 草むしり 月を観る
今日は一段と気温が上がった。母は昏睡を続けているが幸い肺炎を免れている。夕刻の仕事を終えると庭仕事に樹下美術館へ行った。
妻が先に来ていて、水を遣ったり草を取ったりしている。バトンタッチという顔は汗まみれで、髪や泥や葉っぱの切れ端がくっ付いていた。
さて、草取りは一本でも余計に取らずには居られない。そう言えば病院時代の高知の同僚は草取りといわずに草むしりと言ってたな、と思い出した。
一時間するかしないかで日が落ちかかり月が出ていた。上弦のうちは早い時間が見頃だという。吉田拓郎の旅の宿の二人は明るみの残るうちから飲んでいたのか。またその方が歌の風情も上がりそうだ。
草取り終えて手なぐさみにと地面にポケットカメラを置いて自分を撮ってみた。
樹下の花 夏を彩る
花数少なくなる夏の庭。いま濃い緑の中でちゃんと目だって咲いているのは、花の心得通りだ。
 キキョウ
キキョウ
暑さ気にせずいつも賑やか

ムクゲ
沢山の蕾を付けて秋に向かってスタートした。

カノコユリ
最も遅く咲く百合の可憐。

カシワバアジサイ
真っ白に開化して二ヶ月、グラデーションを見せながらまだ粘る。
人の行き交い 明日から8月 夏の思い出
夏がくれば思い出す はるかな樹下美術館
緑の中にうかびくる 館つつまし野の小径
桔梗と木槿の花が咲いている
夢見て咲いている木もれ陽の庭
野バラの色にたそがれるはるかな樹下美術館
(名曲夏の思い出を拙い替え歌にしました。夏の思い出は、わが新潟県高田市・現上越市がお生まれという江間章子さんの作詞です。江間章子さんゴメンナサイ)
明日はもう8月。本日新潟市からお見えのお客様はこれから長野県へ向かうと仰いました。昨日は長野市からと、人の行き交う夏本番。晴れれば雲高く、どこかに秋の気配も感じられます。
スタッフによれば7月のお客様は昨年のちょうど倍だったそうです。皆様には心から感謝致してます。アッシュさん、ジャックランドさんご紹介あり難うございました。
雨がようやく止んで
ひどい水害をもたらして数日来の雨は止んだ。滅多に水につからない上越市大潟区の田畑も水びたしだった。
新潟県では中越地方を中心に、上越市でも吉川区や保倉川水系などで甚大な水害となった。今年は特に自然の猛威を知らされる。
 午前、往診帰りの田畑 大潟区里鵜島
午前、往診帰りの田畑 大潟区里鵜島

ようやく雨が上がり、鳥たちが活発になった

次第に夏らしい空に
午後から晴れてきて、樹下美術館の裏手の田んぼではツバメが休みなくヒナに餌を運んでいた。豪雨続きで親子ともお腹が空いていたにちがいない。
夕刻近く、長野県から可愛い赤ちゃんをベビーカーに乗せた若いご夫婦がいらしてた。上越市へ海を見に来られたということ。たまたま食事をした店に置かれたジャックランドで当館を知り、寄ってくださったと。
 可愛いお嬢ちゃまが一緒のナイスファミリー
可愛いお嬢ちゃまが一緒のナイスファミリー
またいらしてください、ありがとうございました。
潟町にチョウトンボ 樹下美術館にはアマガエル
今日の上越市は涼しく、晴れ間の見える昼過ぎでも28度前後だった。その晴れの庭にチョウトンボ。池の周囲に多く見かけるが庭で見るのは珍しい。二羽で来て15分くらい飛ぶとそれぞれ休み、一度はお洒落なカサブランカに止まった。
涼しくとも美術館の庭はぐったりしている花がある。予報は降りだったが外れもあろう、と夕刻に撒水を始めた。すると間もなくざーと夕立が来て、間髪を入れずあちこちでアマガエルが鳴き出した。
昨日は鉱物今日は小動物、なんでも少しずつだ。
 潟町の自宅の庭にチョウトンボ  トクサでうっとりしている |
 カサブランカに止まるなんて  田んぼを見下ろすデッキにも |
赤い月 高田高校の山崎先生
良く晴れた一日、少しく風が吹いて、日中は家より外が楽な時間もあった。いよいよお年寄りの脱水症(発熱、食欲途絶)が始まった。今日は三件の往診先で点滴をした。いずれも急で夏は本当に油断が出来ない。
さて今夕の満月を楽しみにしていた。月の出を家の前の道路から見ることが出来た。出たばかりの月は驚くほど赤く、家並みの真上だったので大きく見えた。あまりの赤さに、お向かいの奥さんがあれは何ですかと仰ったほどだった。

ルナ・ロッサ(Luna Rossa) 赤い月はシャンソンにもある
ルナ・ロッサと言へば、テラ・ロッサも思い出す。双方ともイタリア語で、テラは土でロッサは赤。赤い土テラ・ロッサは地中海地方やブラジルに見られるぞ、と高校時代に山崎静雄先生の世界地理で教わった。
ロングさんとあだ名された先生は数学がメインだったが地理も教わった。アルゼンチンの首都ヴェノスアイレスはスペイン語で良い空気という意味なんだ、シュヴァルツ・ヴァルトはドイツ語で黒い森だとも習った。
先生が話をされるとそこへ行ってみたくなった。
一年生の時の担任でもあった先生。その年の後半、私の結核が分かった時に親身になって心配してくださった。背が高く山岳部の指導もされたと思う。
授業は常に熱心で思い出深い。
ハチの季節 くちなし
昨日の菅氏の談話は今朝様々に伝えられていた。激しい批判は構わないが、メジャーメディア自身もエネルギーについて独自の研究や展望をもっと語ってもらえればと感じた。
暑さの中、ハチが勢いを増している。畑で刺された、洗濯物を触ったら刺されたという方が見える。中にはそのつど気を失ったり、喘息やひどい下痢嘔吐になる人がいて油断出来ない。予め抗アレルギー薬を持っている人もいる。
そのハチに夕刻の庭で妻が服の上から肩をさされた。今日はスタッフの女子会ということ、痛い痛いといいながら塗り薬持参で出かけた。

クチナシが夕暮れの庭に香る。
十年前に買った60センチばかりの樹は、二メートルを越える丈になった。
。
今日は芝生の草取り カトリス
午前に妻は花壇を、夕刻の草取りは妻が花壇の続き、私は芝生をしました。芝生はざっと見た目と注意して見た目ではかなり違います。
樹下美術館のは、一見それなりにきれいですが、場所によって雑草も大いに混じっています。芝刈りとともに雑草取りも欠かせません。
この数年ノスミレの混入が目立つ場所があり、少しずつ取っていましたが今日で一応取り切りました。
しかし雨が降れば再び生えてくるでしょう、その時はまた“カトリス”を下げることにします。
夏の庭仕事の面倒はなんといっても暑さと蚊ですね。妻は先日電池式携帯虫除けを買ってきました。効くということでしたので本日私も買いました。
キンチョウの“カトリス”でした。音も匂いもなく、もちろん煙もみえません。半信半疑でしたが、蚊は寄ってきませんでした。何事も遅れがちな私は大いに驚いた次第です。
カトリス=蚊+テトリス、蚊打ち落としゲーム。キンチョウの名付けは感心してしまいます。
間もなくスタッフによる三回目の芝刈りです。
草取りの夏
長雨から昨日の曇天、そして本日午後から晴天となった。妙高山はと見たが、今日もはるか雲に遮られて南葉山さえ見えなかった。これも長雨後の高い湿度のせいなのだろうか。
午後に見た大潟区の水田はいっそう青々として、農道のタチアオイとぴったり息があっていた。
田で草取りが行われていた。イネの列の隙間に沿って発動機の道具を押して進む。患者さんから聞いたばかりだが、草は抜き取らずに土にすき込んで行くという。昔は暑さの盛りに中腰となり鉄の熊手のようなもので掻いて、それは大変だったと。
手持ちの道具も今や珍しいかもしれない。大きな農業用の車で進む草取りもよくみる。車で入ってもイネを倒さないのはどうなっているのだろう。
夕刻、仕事が終わると美術館へ飛び、庭の草取りをした。見ぬ間に大挙して草が生えている。攻め込まれているようで、やや興奮しながら一時間少々取った。長袖シャツでヤブ蚊に備えたが、頭のてっぺんと耳たぶと額を刺された。
草取りなくして庭は成り立たない。それなりにやっていてものんびり庭を見ているヒマがない。明日の午前中、今度は私がと妻が言った。
梅雨の宝石アジサイの盛り
ひどい降りを交えて長雨の気配です。今日は肌寒いくらいの低温、貴重な節電日だったのかもしれません。
樹下美術館隣接の庭でアジサイが賑やかになりました。いくら雨に降られてもしっかり花を保つ優しくも根性の花、アジサイ。西洋名ヒドランジアとは水を入れる器ということですので、たしかに雨に強いわけです。
これから花色を変えて行き、最後ははやり痛みます。盛りの花を見ていると、けなげで美しく“梅雨の宝石”と呼ばれるのが分かるような気がします。
降られてもまだまだと言ふ紫陽花
 ダルマバノリウツギ、向こうに濃い甘茶  クレナイ  堂々としてきたカシワバアジサイ  ダルマバノリウツギ |
 普通?のヤマアジサイ  ベニガクアジサイ  藍の空?紫姫?  清澄(キヨスミ)サワアジサイ |
“藍の空”は植えて3年目、大変小ぶりなアジサイです。花の脇にあった札に辛うじて藍の空と読めたのですが、業者さんの名付けかもしれません。
清澄山は千葉県にあるそうです。
アジサイの名の同定はとても難しく思いました。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 高齢者、昔話
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。
- 週末の種々。
- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。
- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。
- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。
- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。
- 昨日レコード、今日白鳥。
- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。
- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。
- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。
- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天
- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。
- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。
- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。
- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。
- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。
- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。
- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」
- 長生きのお陰色々。
- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月